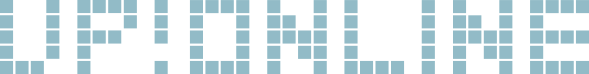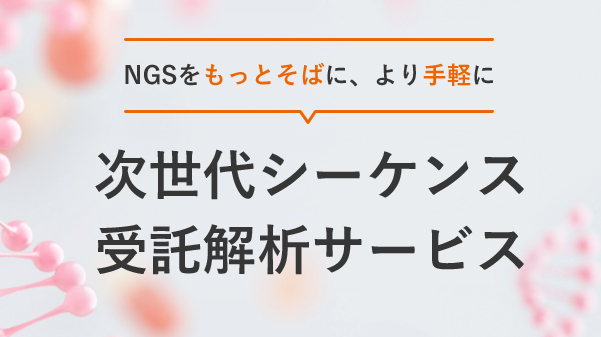東京大学名誉教授
1979年より製薬会社中央研究所、1987年より現在まで東京大学(農学生命科学研究科)、2016年から2020年まで早稲田大学にて研究されてきた。素朴な生物学の影を残した時代から、全生物のゲノム情報を含む生命科学の基礎と産業応用の飛躍の時代になった。本コラムでは大学や企業での経験も交えながら、専門分野のエピジェネティクスを含めた自由な展開をお願いしました。
第四十七回 歌を忘れたカナリア
“歌を忘れたカナリアはうしろの山に捨てましょうか♪・・” 見るからに色褪せた絵本の中のカナリアが困った顔をしていた。鳴かないからと言って何も捨てることはないのでは!と、勝手な歌詞に納得できなかった子供の頃の思いは、今でも他人事とも思えず続いている。
近くの公園に出かけると“ホーホケキョ、ケキョケキョ・・”と鶯(ウグイス)の見事な鳴き声が聞こえてくる。春先には上手く鳴けなかった鶯が、すっかりプロの囀りだ。少し足を伸ばし畑に囲まれた野原まで行くと新緑の木々の間から“ケーン・ケーン”と甲高い少し錆びたオス雉(キジ)の鳴き声も聞こえてくる。
成熟オスの容姿や鳴き声は“性淘汰”として知られる進化のメカニズムの中で発達してきたとされる。雉のオスについて、“顔が裸出し赤色、頸・胸・下面全体は暗緑色、背面の色彩は甚だ複雑美麗・・”と丁寧な説明(広辞苑・第6版)だが、メスの項では“淡褐色で黒斑があり尾は短い”とだけでそっけない。
看板とはあまりにも異なり、擦り切れた尾羽の雉や孔雀、艶を失ったボソボソのたてがみのライオンなど、動物園の檻の中の生気を失ったオスの動物たちにはがっかりしたものだった。飼育下で豊富な餌を与えられ自分で探す必要もなく、敵もいない。緊張も無く運動不足も加わると野生のオスらしさが薄れてきても仕方ないと思う。近年では動物園側でも、餌を隠し動物に探索させるなど様々な工夫を凝らしているようだが、野生の状態を取り戻すことはそう簡単ではなさそうだ。