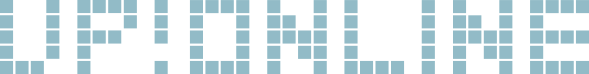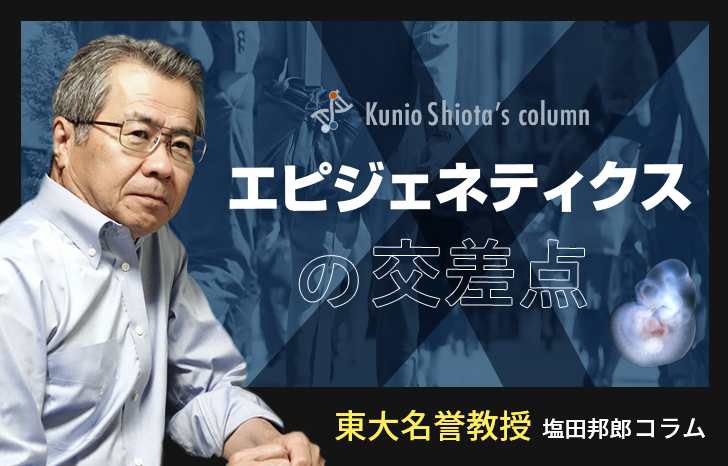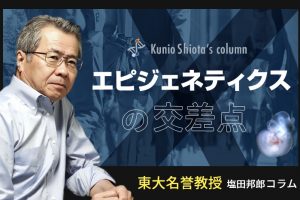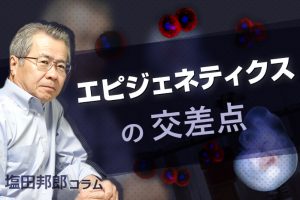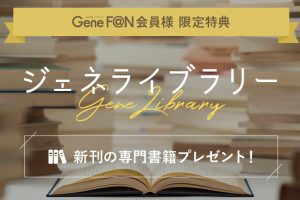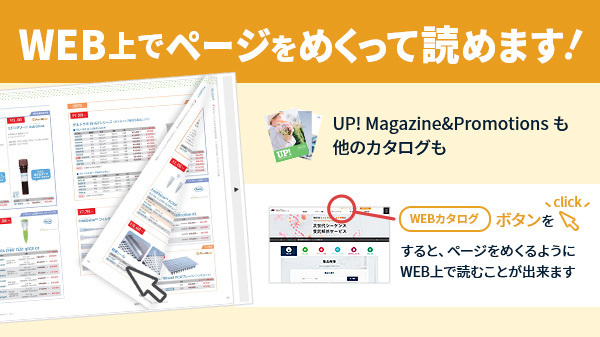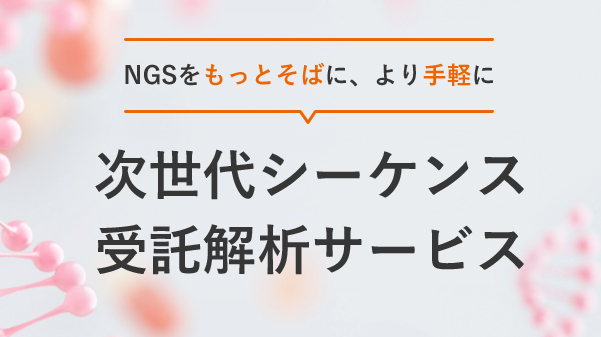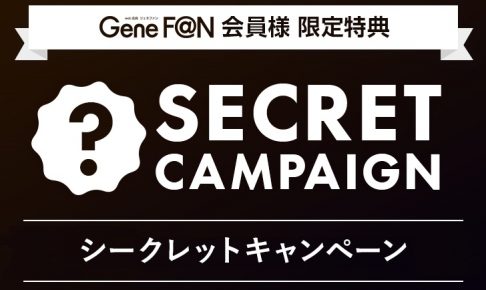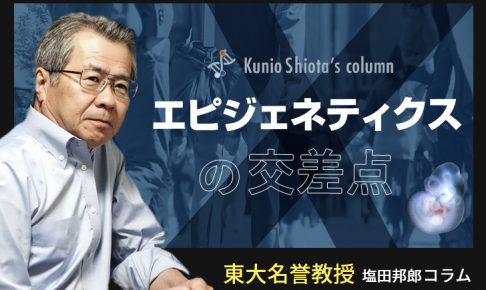塩田 邦郎(しおた・くにお)
東京大学名誉教授
1950年鹿児島県生まれ。博士(農学)。79年東京大学大学院農学系研究科獣医学専攻博士課程修了後、武田薬品工業中央研究所、87年より東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻生理学および同応用動物科学専攻細胞生化学助教授、98年より同細胞生化学教授。
2016年早稲田大学理工学研究院総合研究所上級研究員。哺乳類の基礎研究に長く携わり、専門分野のエピジェネティクスを中心に、生命科学の基礎研究と産業応用に向けた実学研究に力を注ぐ。2018年より本サイトにて、大学や企業での経験を交え、ジェネティクスとエピジェネティクスに関連した話題のコラムを綴っている。
第八十一回 エピジェネティクスの古時計
「梅は咲いたか、桜はまだか」と気にしているうちに、ふと気づけば梅はすでに咲いている。時間の流れは子どものころはゆっくりに感じられ、大人になるとあっという間に過ぎ去るように思える。この違いは単なる感覚の問題なのか、それとも生物学的な変化が関係しているのだろうか。
時間の流れの感じ方は心理的・生理的な要因によって異なる。たとえば、楽しい時間はあっという間に過ぎるが、退屈な時間は長く感じる。子どものころは新しい経験が多くそれぞれの記憶が鮮明に残るため時間が長く感じられる。一方、大人になると日常がルーチン化し新しい経験が少なくなるため時間が短く感じられる。このように、記憶の密度の違いが関係しているのかもしれない。
あるいは、若いころは神経伝達の速度が速く、情報を細かく処理できるためかもしれない。たとえば、打ち返されたテニスボールへの反応が遅れることが増えると、加齢に伴う神経伝達速度の低下を実感する。このように、脳の情報処理の速度や量の変化は、心理的な要因というより、生理的な課題といえるだろう。さらに、遺伝子発現が絡む生理学的変化とも関連している可能性がある。たとえば、脳の海馬など記憶を司る部位では、DNAメチル化(注1)やヒストン修飾といったエピジェネティクスの老化が関係しているのではないか。この変化によって、記憶の保持や時間の知覚に影響が生じる可能性がある。