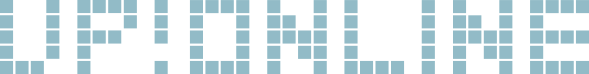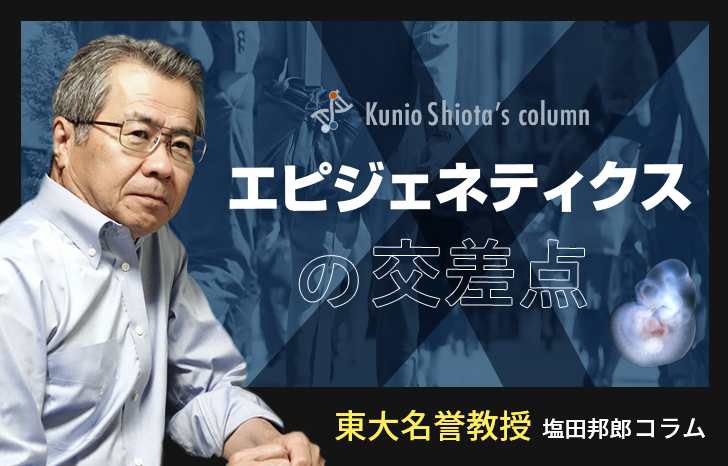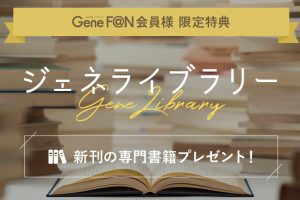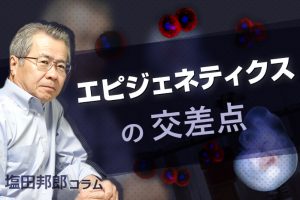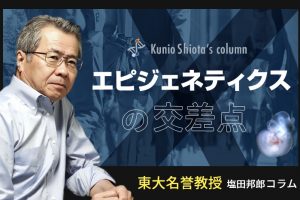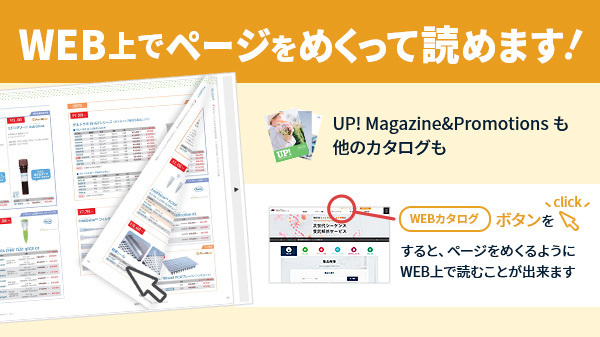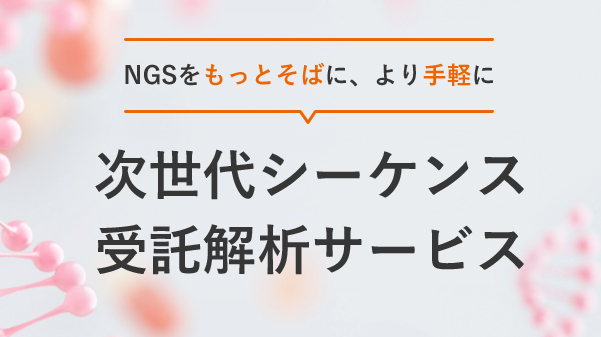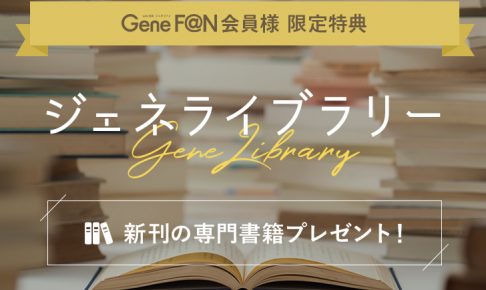塩田 邦郎(しおた・くにお)
東京大学名誉教授
1950年鹿児島県生まれ。博士(農学)。79年東京大学大学院農学系研究科獣医学専攻博士課程修了後、武田薬品工業中央研究所、87年より東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻生理学および同応用動物科学専攻細胞生化学助教授、98年より同細胞生化学教授。
2016年早稲田大学理工学研究院総合研究所上級研究員。哺乳類の基礎研究に長く携わり、専門分野のエピジェネティクスを中心に、生命科学の基礎研究と産業応用に向けた実学研究に力を注ぐ。2018年より本サイトにて、大学や企業での経験を交え、ジェネティクスとエピジェネティクスに関連した話題のコラムを綴っている。
第八十三回 光とドーナツの穴を巡って
青葉が眩しい光の季節だ。毎年この時期から「冷やそうめん」の始まりになるのだが、他にも麦茶に入れるなど氷をたくさん使うから、冷蔵庫付属の製氷器で作る量では足りない。捨てずにとっておいた某メーカーの市販の味噌が入っていたプラスチック容器(底面積60 cm²(縦10×横6 cm))の出番である。この味噌容器は薄いが丈夫で冷凍庫内でも収まりが良く、製氷時間も短い。約300 mLの水を入れ、冷凍庫で凍らせると、冷やそうめんの桶に入れるのにちょうど良い大きさの跳び箱のような形の氷が出来上がる。
目はカメラに例えられるが、それは逆で、カメラは目を真似て造られている。目もカメラも、光はレンズを通過して内部に入り、奥にあるセンサーで捉えられる。ひと昔前のセンサーはフィルムで、通常の撮影ではASA 100のフィルム(ASAはAmerican Standards Associationによるフィルム露光指数)、薄暗い中では感度を上げてASA 200〜400のフィルムを使ったものだった。しかし、フィルムのASA感度を上げれば粒子が粗くなり、写真がゴツゴツしてくる。感度を上げる目的ではなく、写真にゴツゴツ感を出すためにASA1600など超高感度フィルムを、逆に滑らかな写真にするために粒子の細かいASA 25など低感度フィルムを、と粋がって探し求めたものだった。