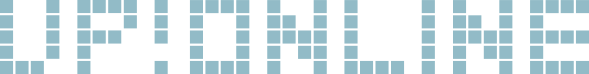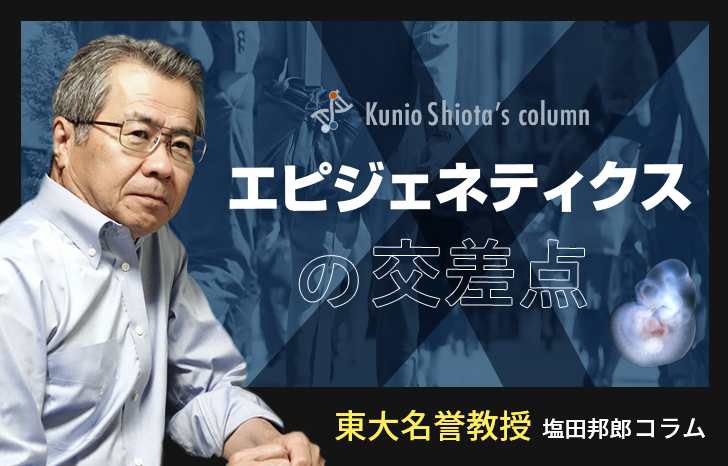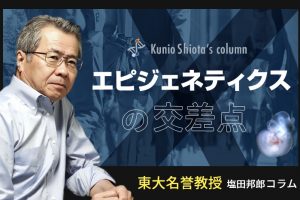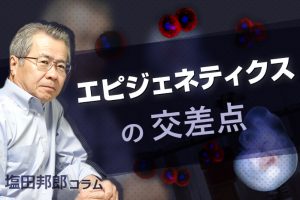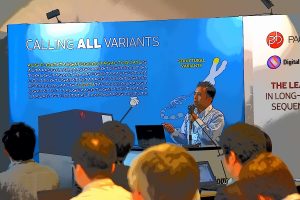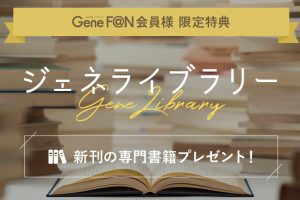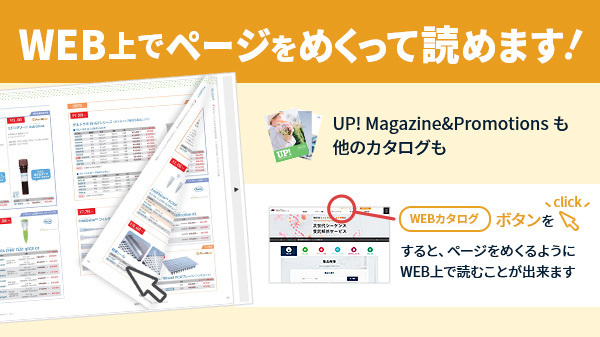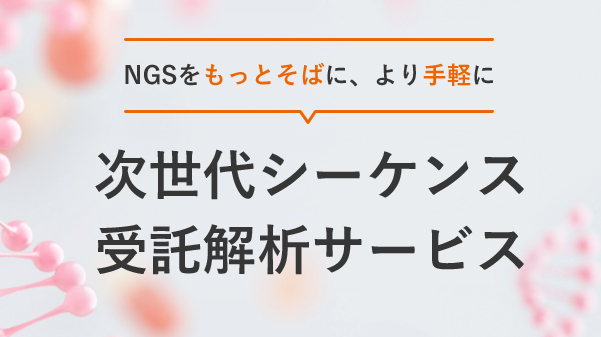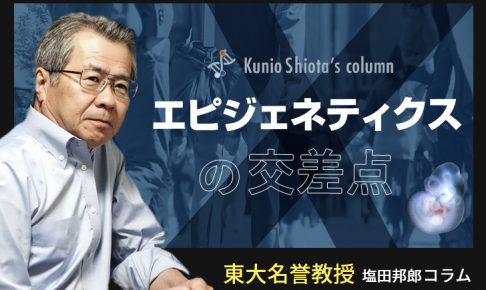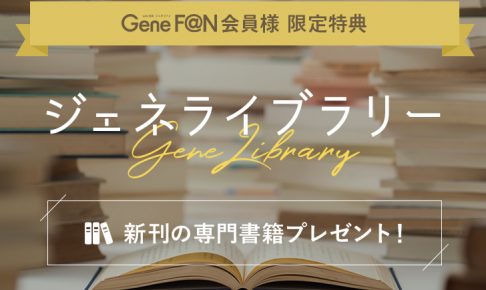塩田 邦郎(しおた・くにお)
東京大学名誉教授
1950年鹿児島県生まれ。博士(農学)。79年東京大学大学院農学系研究科獣医学専攻博士課程修了後、武田薬品工業中央研究所、87年より東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻生理学および同応用動物科学専攻細胞生化学助教授、98年より同細胞生化学教授。
2016年早稲田大学理工学研究院総合研究所上級研究員。哺乳類の基礎研究に長く携わり、専門分野のエピジェネティクスを中心に、生命科学の基礎研究と産業応用に向けた実学研究に力を注ぐ。2018年より本サイトにて、大学や企業での経験を交え、ジェネティクスとエピジェネティクスに関連した話題のコラムを綴っている。
第八十五回 空気を忖度する
イスラエルのネタニヤフ首相が、トランプ米国大統領をノーベル平和賞候補に推薦した。7月7日にホワイトハウスで行われた会談の際、「次々に平和を築き上げている」と持ち上げ、ノルウェー・ノーベル委員会に宛てた推薦書簡のコピーを直接手渡したという(朝日新聞朝刊2025年7月7日)。ノーベル平和賞を欲しがるトランプ氏への“贈り物”なのか、イスラエルに軍事援助を続けつつ、イランの核濃縮施設を直接攻撃したことへの感謝のつもりなのか。冗談にもならず、呆れるほかない。
「私たちの社会は“空気”によって支配されている」──これは思想家・山本七平の言葉である。「あの場の空気ではそうせざるを得なかった」「あの場の空気を知らないから、あなたはそんなことが言えるのだ」と書かれている(山本七平ライブラリー①『空気の研究』文藝春秋)。この本を初めて読んだ1970年代には、“空気”は日本社会の特殊性だと思っていたが、どうやらそうでもないらしい。“空気”は立場や地域、世代といった共通項を持つ集団で自然と醸成される。異なる“空気”を持つ社会間では理解しあえず、時に対立にまで至る。つまり“空気”は、大小さまざまな“村社会”に普遍的に存在するのだ。