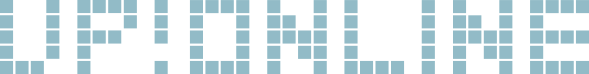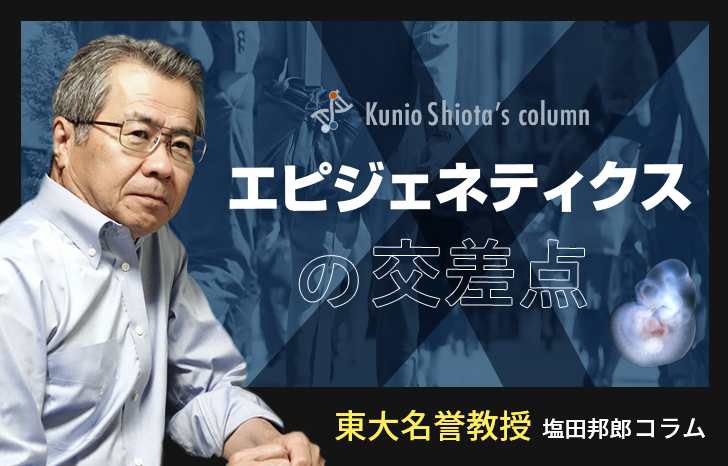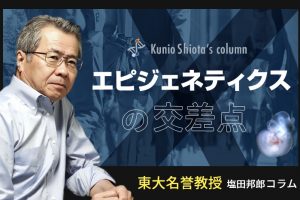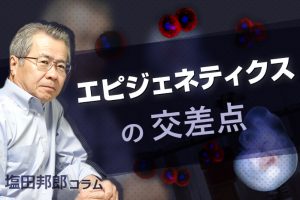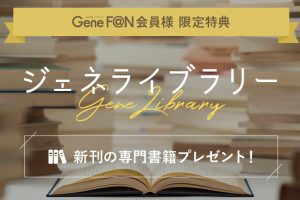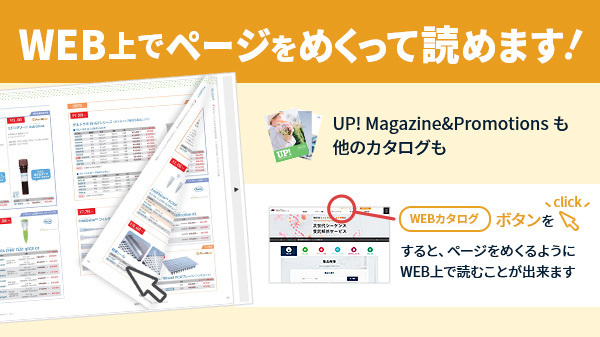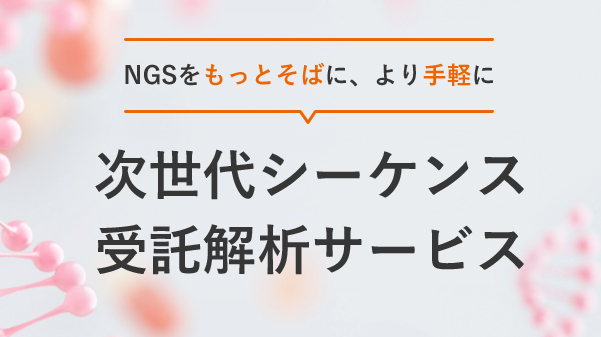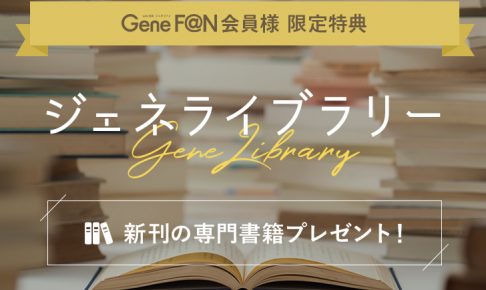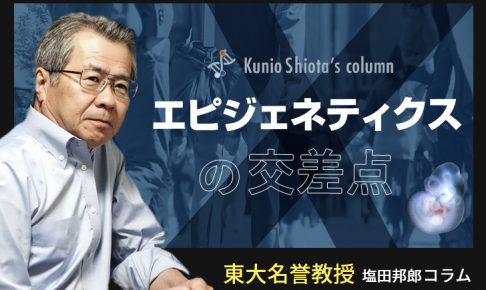塩田 邦郎(しおた・くにお)
東京大学名誉教授
1950年鹿児島県生まれ。博士(農学)。79年東京大学大学院農学系研究科獣医学専攻博士課程修了後、武田薬品工業中央研究所、87年より東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻生理学および同応用動物科学専攻細胞生化学助教授、98年より同細胞生化学教授。
2016年早稲田大学理工学研究院総合研究所上級研究員。哺乳類の基礎研究に長く携わり、専門分野のエピジェネティクスを中心に、生命科学の基礎研究と産業応用に向けた実学研究に力を注ぐ。2018年より本サイトにて、大学や企業での経験を交え、ジェネティクスとエピジェネティクスに関連した話題のコラムを綴っている。
第八十九回 働いて、働いて
自民党の総裁に選ばれた高市早苗氏の「働いて、働いて・・・働いていく!」、なんと小気味よい響きだろう。満員電車に揺られながら、「24時間戦えますか」の広告に囲まれた時代の私には、懐かしく、さわやかにすら感じられる。若い頃は実験で徹夜もあり、その後は予算申請、講義の準備などに追われていたことなど思い出した。
本年度のノーベル賞の受賞者 北川進氏や坂口志文氏はともに74歳で「働いて、働いて」世代である。いくつかの記事には、「いっぱいやる事がある」に悲観することなく、「創造的で楽しい」と積極的に楽しむ姿勢が紹介されている。
坂口志文氏の業績は免疫系の暴走を抑える制御性T(regulatory T)細胞の発見だ。Tは胸腺(Thymus)由来を意味する。胸腺は心臓の前方左右にある葉状の器官で、思春期には30〜40 gだが成人期以降には次第に退縮し、老人では大部分が脂肪に置き換わる。生涯にわたって機能するというわけではないから、乱暴に言えば胸腺は生存上「無くてよい器官」とも捉えられた。しかし、生後すぐに胸腺を除去したマウスは卵巣などいくつかの組織に炎症を起こすことも知られており、炎症を起こさないようにする何らかの役割を担っているのでは?との淡い推測もあったようだ。