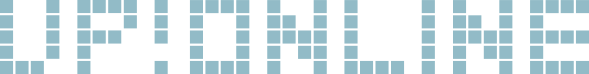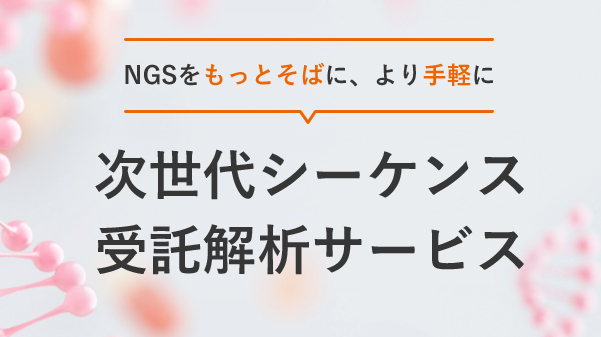東京大学名誉教授
1979年より製薬会社中央研究所、1987年より現在まで東京大学(農学生命科学研究科)、2016年から2020年まで早稲田大学にて研究されてきた。素朴な生物学の影を残した時代から、全生物のゲノム情報を含む生命科学の基礎と産業応用の飛躍の時代になった。本コラムでは大学や企業での経験も交えながら、専門分野のエピジェネティクスを含めた自由な展開をお願いしました。
第三十七回 胞衣信仰からゲノム信仰へ
千葉県佐倉市にある武家屋敷を訪れた時、直径が約20cmの素焼きの皿が目についた。敷地から発掘された武士の家族の胞衣(えな)皿と記されていた。お産の時に体外に排出される胞衣(胎盤や胎児を包んだ膜などの後産のこと)は神聖なものとして大切に扱われ、この皿に胞衣を入れ土中に葬り子供の成長と子孫の繁栄を願ったという。平城京跡からも胞衣を入れる壺が見つかっており、胞衣を奉納した神社も各地に存在する。乳児の死亡率が高かった時代、支配者階級から庶民まで受け入れられてきた“胞衣信仰”とも呼べる古くからの風習だ。
受精卵が分割を繰り返し数百個の細胞の塊になると、外側の層の細胞は胎盤の基になる栄養膜細胞に、内側の細胞は胎児の体を構成する細胞になる。したがって胎盤は受精卵由来、あるいは、胎児由来であることは先のコラム(第36回)でも記した。
現代の信仰とみまがうものの1つに、新たな胎児のゲノム診断である新型出生前診断(NIPT)がある。NIPTが可能になったのは母親の血液中に胎児のDNAが存在するからだ。妊婦の末梢血液に含まれる胎児DNAを調べるため、胎児組織や胎盤などへのダメージを避けることができるから、無侵襲の胎児診断(non-invasive prenatal testing: NIPT)と呼ばれている。