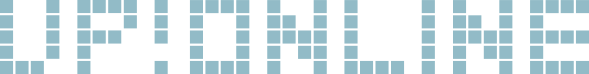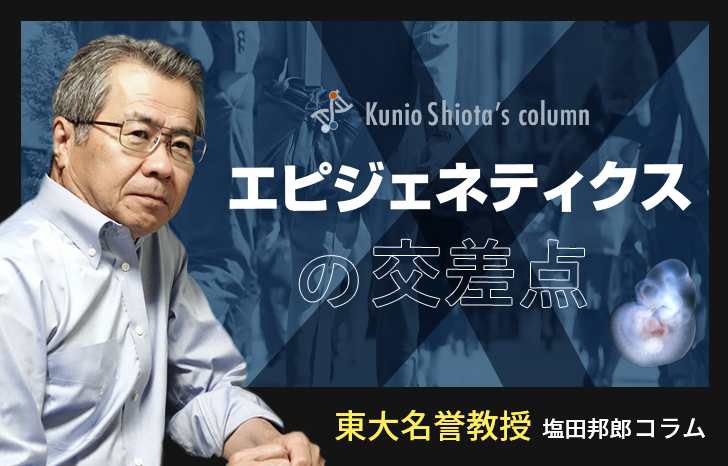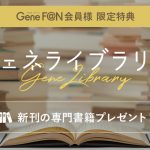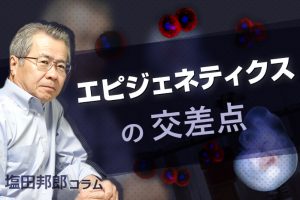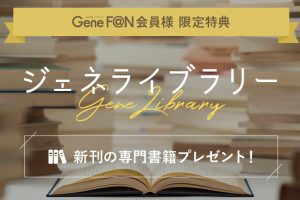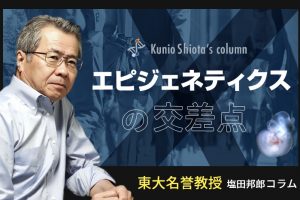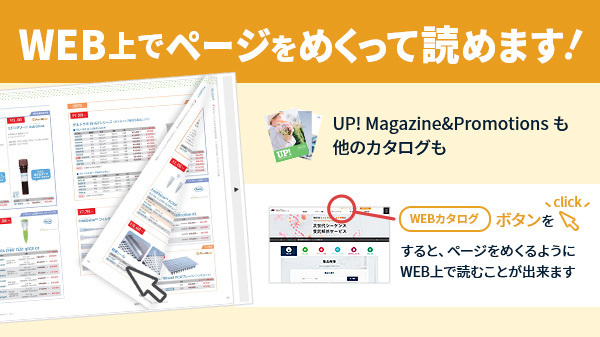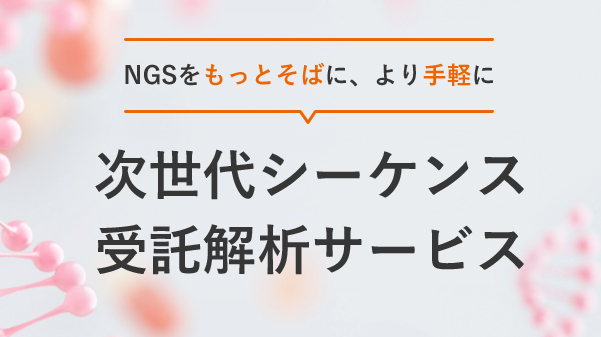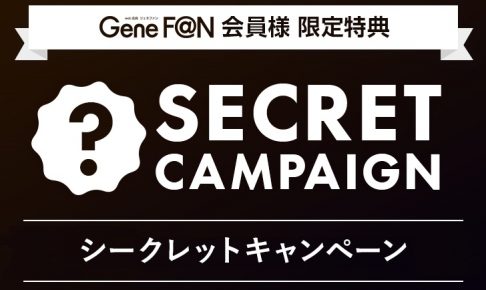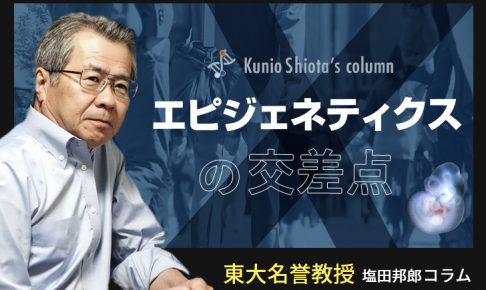塩田 邦郎(しおた・くにお)
東京大学名誉教授
1950年鹿児島県生まれ。博士(農学)。79年東京大学大学院農学系研究科獣医学専攻博士課程修了後、武田薬品工業中央研究所、87年より東京大学農学生命科学研究科獣医学専攻生理学および同応用動物科学専攻細胞生化学助教授、98年より同細胞生化学教授。
2016年早稲田大学理工学研究院総合研究所上級研究員。哺乳類の基礎研究に長く携わり、専門分野のエピジェネティクスを中心に、生命科学の基礎研究と産業応用に向けた実学研究に力を注ぐ。2018年より本サイトにて、大学や企業での経験を交え、ジェネティクスとエピジェネティクスに関連した話題のコラムを綴っている。
第八十二回 春眠に守られて
ヒヨドリの“ピーー”と甲高い鳴き声に起こされていたのは、冬の寒さが和らぎかけてきた、つい先ごろまでの毎朝の出来ごとだった。メジロのためにミカンの切れ端を桜の枝に刺しておくと、ヒヨドリが自分のものと勘違いして大声で催促する賑やかな朝の時間だった。それも、椿が散り始め桜の開花が近づくころになると、ヒヨドリの姿はパタリと途絶えおかげで心地よい眠りに浸れている。「春眠暁を覚えず、処処に啼鳥を聞く」(孟浩然『春暁』)である。
睡眠はクラゲから線虫、ハエ、ゼブラフィッシュ、げっ歯類、人間に至るまで、すべての神経系を持つ動物が進化上、獲得した行動である(注1)。なぜ睡眠が進化したのか、またどのような根本的な機能を果たしているのかは未だ謎に包まれている。明らかなことは、脳が適切に機能するためには睡眠が必要であり、覚醒はコストのかかる状態であり、無限に持続することはできないということである。
神経細胞を含むすべての細胞のゲノムDNAは、常に壊れる危機に瀕している。細胞増殖に先立ち、ゲノムDNAは複製されることになるが、何しろ30億塩基も連なっているのだ。幸いにもDNA複製のエラーが生じない(DNA複製に関わる各種酵素自身が間違いを起こさない)ように、二重三重のエラー防止の安全策が備わっている。それでも、仮にDNA複製時に0.01%の間違いが生じるとすれば、30万箇所に変異が生じてしまうことになる。増殖が盛んな、例えば、血球系や皮膚の細胞などの場合には深刻な問題になるだろう。