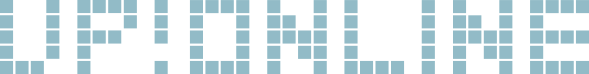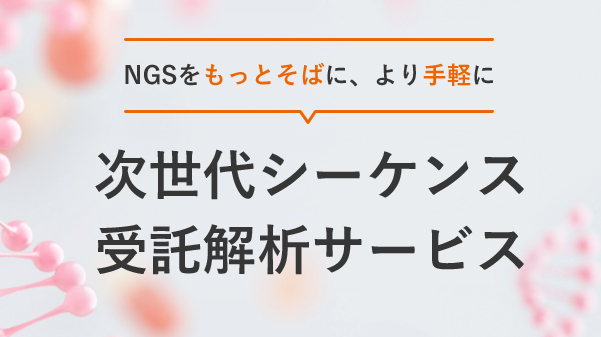東京大学名誉教授
1979年より製薬会社中央研究所、1987年より現在まで東京大学(農学生命科学研究科)、2016年から2020年まで早稲田大学にて研究されてきた。素朴な生物学の影を残した時代から、全生物のゲノム情報を含む生命科学の基礎と産業応用の飛躍の時代になった。本コラムでは大学や企業での経験も交えながら、専門分野のエピジェネティクスを含めた自由な展開をお願いしました。
第六十回 キリマンジャロの老豹
本を買い求めて帰宅して読み始め、あれ? どこかで読んだことがあると思いながら、本棚を見ると同じ本が見つかることがある。コーヒーカップを手に、モノトーンの北向きの部屋で、重ねて購入した本に向かいながら、これが歳をとるということ? とまるで一人芝居をしているような錯覚に陥る。歳をとり始めて初めて戸惑う場面だ。
歳をとってからも(がんなど特殊な細胞を除いて)ゲノムDNAは若い頃と同じはずだ。受精卵の段階から胎児期、児童期、青年期、壮年期を経て、老年期に至っても、生涯にわたって全身の細胞のゲノムDNAは不変だ。大きく変わるのは、エピジェネティクスによるゲノムDNA利用のあり方なのだ。
DNAメチル化はヒストン修飾と相互に依存している(第13、15、31、35、 36、48、49回コラム)。発育・成長に伴いゲノムDNAの随所に、主にDNAメチル化と各種ヒストン修飾によるエピジェネティクス修飾が施され、細胞の種類に特有のエピジェネティクス模様(エピゲノム)が出来上がる。エピゲノムは細胞の世代を超えて継承される安定した装置だが、環境に応じて変化し得る(注1)。生涯にわたるエピゲノムの変化が、各細胞の活動・維持に必要(あるいは不要)な遺伝子領域を指定するのだ。生活習慣病や認知症など様々な病や老化と関連づけられるエピジェネティクス領域も特定できる。